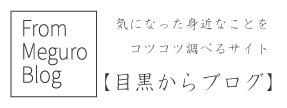“「今夜はこれで食べてみたいのです」
源斉は懐から三方に折り畳んだ懐紙を取り出すと、そっと中を開いた。
まあ、と澪(みお)が声を洩らす。「唐三盆」と呼ばれる、
目玉が飛び出すほど高価な、真っ白な砂糖だった。
「今日、吉原の翁屋の楼主の診察に呼ばれまして。
お相伴に 預かったものを持ち帰ったのです。
ここでこうして食べたくてね」
澪を見て、にこにこと笑うと、源斉は二つの心太(ところてん)に
砂糖をさらさらと振りかけた。
「花魁たちはこうして食べるのだそうです。
磯の香りとはそぐわないかも知れないけれど、
目先が変わって良いでしょう?」
澪は器を取って、目の高さに持ち上げてみた。
透明な心太の上に乗った白い砂糖が、青白い月の光に
照らされて雪のように映った。
「こいつはまるで雪ですね、
日にちこそずれちまったが、まさに『八朔の雪』だ」
脇から源斉の器を覗き込んで、種市が溜め息交じりに言った。
八朔の雪?と首を傾げている澪に、源斉がふっと頬を緩めた。
「八月朔日(ついたち)に吉原の遊女たちが
白無垢を着ている情景を『八朔の雪』と言うのです。
残暑厳しい季節に雪を思わせる風情から、そう呼びのでしょうね」
なるほど、と澪は、うっとりと月に翳した心太の砂糖を眺めた。”
(以上、「八朔の雪」より引用)
なんと風情のあるシーンだろう。
個人的にはこのシーンが一番好きで、この本の雰囲気を感じるにも
このシーンがベストだと思い引用させてもらった次第です。はい。
本日、『八朔の雪/高田郁』を読了した。
この本の舞台は江戸時代。
主人公、澪(みお)は大阪生まれの18歳。
幼い頃に、水害で両親を失い、一人行き場も無く街を彷徨っている
ところを「料理屋・天満一兆庵」の女将、芳に助けられる。
行くあての無い澪は、その縁と店主、女将の優しさで一兆庵で
奉公することになる。
ところが、その数年後、一兆庵は火事で焼けてしまう。
その後、店主の息子が任されている支店を頼って3人は江戸に
来るが店はなく、息子の若旦那も行方知れず。
心労がたたって店主は死んでしまう。
その後、縁あって知り合った蕎麦屋「つる家」の主人・種市に
請われて澪は「つる家」で働き始める。
そこからは様々な料理のレシピや上方と江戸の文化の違いなどなど
を織り交ぜながら人情味溢れる物語が進行する。
時代小説らしく、その当時の雰囲気を感じられることと、
なんと言っても、登場人物の優しいやりとりが実にイイ。
読みながら笑顔になってしまう。
ちなみに冒頭の心太(ところてん)の件は、
通常、関東では心太を酢醤油で食べるのに対して、
大阪では黒砂糖などの蜜で甘く食べるというところからきている。
実はこの歳まで僕も知らなかった。
茨城生まれの僕は、心太はしょっぱい食べ物と認識していたのだが、
大阪(というか西)では甘くして食べるのがスタンダードだそうだ。
透明の心太に白い砂糖をかけた姿が、
八月朔日(ついたち)に吉原の遊女たちが白無垢を着ている情景=八朔の雪
のようだなんて、なんとまぁ豊かな表現だろう。
実は僕がこの本を知ったのは、思いっきり後追いで。
先日、テレビ朝日系列で放映された特別ドラマ「みをつくし料理帖」を
たまたま観て、あまりに面白かったので、その原作を読んでみよう
ということで知ったのだ。
この「みをつくし料理帖」ってのはシリーズで何冊か本が出てるんだけど、
ドラマは、まさに「八朔の雪」をそのままドラマにしてる感じ。
いや~、久しぶりに本を読んだ。
時代小説にいたっては、百田尚樹さんの『影法師』以来だ。
ホントに面白かった。やっぱり本は読みやすいに限る。
次は続編2作目の「花散らしの雨」を読んでみようと思う。